朝起きられないときに考えられる原因
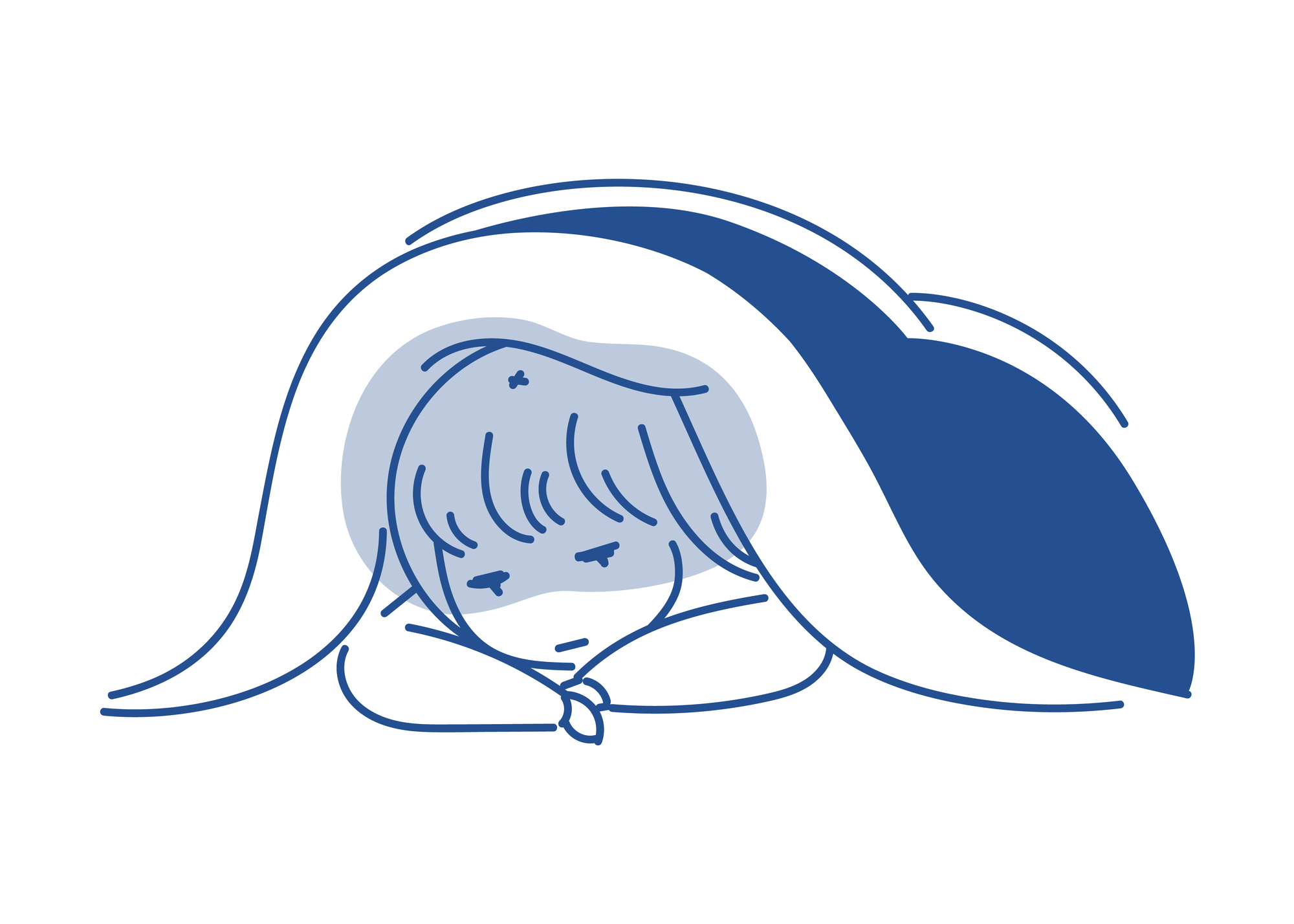 冒頭で触れたように、朝起きられない背景には夜更かしや寝不足といった日常的な要因が多く見られます。しかし、その「習慣の乱れ」にはいくつかのパターンがあり、生活の中で意識することで改善できるケースも少なくありません。ここではまず、日常生活の中で起きやすい原因を整理してみましょう。
冒頭で触れたように、朝起きられない背景には夜更かしや寝不足といった日常的な要因が多く見られます。しかし、その「習慣の乱れ」にはいくつかのパターンがあり、生活の中で意識することで改善できるケースも少なくありません。ここではまず、日常生活の中で起きやすい原因を整理してみましょう。
生活リズムや体内時計の乱れ
 夜更かしや休日の寝すぎは体内時計を乱し、朝でも脳や体が「夜」と勘違いしてしまいます。過眠症や起立性調節障害などの病気も関与する場合があります。日中に光を浴びる、毎日同じ時間に起きるなどが改善の一歩です。
夜更かしや休日の寝すぎは体内時計を乱し、朝でも脳や体が「夜」と勘違いしてしまいます。過眠症や起立性調節障害などの病気も関与する場合があります。日中に光を浴びる、毎日同じ時間に起きるなどが改善の一歩です。
※当院でも「夜遅くまでPC作業を続けたら朝起きられなくなった」という相談は多くあります。
慢性的な睡眠不足やブルーライトの影響
 睡眠時間の不足や、寝る前のスマホ利用でメラトニン分泌が抑えられ、入眠が妨げられます。
睡眠時間の不足や、寝る前のスマホ利用でメラトニン分泌が抑えられ、入眠が妨げられます。
睡眠障害
 睡眠時無呼吸症候群や中途覚醒は睡眠の質を下げ、朝の疲労感や日中の眠気を引き起こします。
睡眠時無呼吸症候群や中途覚醒は睡眠の質を下げ、朝の疲労感や日中の眠気を引き起こします。
栄養不足・運動不足
 朝食を抜く、鉄分不足、タンパク質不足はエネルギー不足を招き、朝起きる力が低下します。
朝食を抜く、鉄分不足、タンパク質不足はエネルギー不足を招き、朝起きる力が低下します。
ストレスや生活環境の変化
 ストレスや引っ越し・転職などの環境変化は自律神経の乱れを引き起こし、朝起きられない原因になります。
ストレスや引っ越し・転職などの環境変化は自律神経の乱れを引き起こし、朝起きられない原因になります。
朝起きられないときに隠れている病気
前のセクションでは、生活習慣や環境による原因をご紹介しました。
ですが、中には生活リズムを整えてもなかなか改善せず、背後に病気が隠れている場合もあります。
ここでは、朝のつらさに関係しやすい医学的な原因について解説します。
睡眠相後退症候群
体内時計が後ろにずれ、寝る時間・起きる時間が徐々に遅くなってしまう状態です。夜遅くまでスマホやパソコンを使っていると悪化しやすく、朝は頭がぼんやりして布団から出られなくなります。
閉塞型睡眠時無呼吸症候群
眠っている間に呼吸が何度も止まり、そのたびに眠りが浅くなります。ぐっすり眠った感覚が得られず、朝の目覚めが悪い・日中の眠気が強いといった症状が現れます。
うつ病・抑うつ症状
うつ病では、特に朝に強く症状が出るタイプがあります。体が重く、気力が湧かず、布団から出られない…といった状態が続きます。これは脳内ホルモンや自律神経の働きの変化が関係しています。
慢性疲労症候群
原因不明の強い疲労感が長期間続く病気です。十分に寝ても疲れが取れず、朝起きた瞬間から体が重く感じられます。
高血圧・低血圧
血圧の異常は、朝の立ちくらみやめまいの原因になります。特に低血圧では、朝起き上がるまでに時間がかかることがあります。
甲状腺疾患
甲状腺機能低下症では、代謝が低下し、慢性的な倦怠感や眠気が出やすくなります。女性に多く、気づかないうちに朝の不調の原因になっていることがあります。
その他の睡眠障害
周期性四肢運動障害やレム睡眠行動障害、更年期障害や認知症に伴う睡眠異常も、眠りの質を低下させ、朝起きられない原因になります。体質的にロングスリーパーの方も、夜の就寝が遅いと翌朝の起床が難しくなります。
「朝うつ」かもしれないサインに気づいていますか?
 病気の中でも、特に見逃されやすいのが「朝に強く症状が出るタイプのうつ病」です。
病気の中でも、特に見逃されやすいのが「朝に強く症状が出るタイプのうつ病」です。
前章で触れた睡眠障害や身体疾患とは異なり、心の不調が関わるケースでは、自覚しにくく長引きやすい傾向があります。ここでは、その中でも特徴的な「朝うつ」について詳しく見ていきます。
朝うつによくみられる症状
- 朝起きた瞬間から体が重く、強い倦怠感がある
- 布団から出るまでに時間がかかり、支度がつらい
- 気分が沈み、何をする気にもなれない
- 午後になると少しずつ気分や体調が回復する
うつ病手前で悩んでいる方へ
「これくらいなら大丈夫」と思っているうちに、日常生活に支障が出るほど悪化してしまうケースもあります。
朝のつらさや生活リズムの乱れは、心の不調のサインかもしれません。
我慢せず、少しでも早く相談することが、回復への近道です。
当院では、うつ病治療と、睡眠・不眠外来の両面からアプローチし、症状や原因に合わせたサポートを行います。
カウンセリングや薬物療法だけでなく、睡眠改善のための生活指導やストレスケアも含め、あなたの“朝”を取り戻すお手伝いをいたします。
朝起きられないとき、試してほしいこと
 ここまで、生活習慣や病気、心の不調など、さまざまな原因を見てきました。では、今日から少しでも朝をラクにするためには、何から始めればいいのでしょうか。ここでは、すぐに試せる工夫と、習慣として続けたいポイントをまとめます。
ここまで、生活習慣や病気、心の不調など、さまざまな原因を見てきました。では、今日から少しでも朝をラクにするためには、何から始めればいいのでしょうか。ここでは、すぐに試せる工夫と、習慣として続けたいポイントをまとめます。
今すぐできること
- スマホをベッドから離す:寝る直前のブルーライトを減らし、自然な眠気を促します。
- 深呼吸を3回:息をゆっくり吐くことで副交感神経が優位になり、体が「休むモード」に切り替わります。
- 考えごとは紙に書き出す:頭の中を整理し、気持ちを軽くします。
明日から続けたい習慣
- 就寝1〜2時間前の入浴:深部体温を上げてから下げることで眠りやすくなります。
- 朝食にタンパク質をプラス:魚や卵・大豆製品は睡眠ホルモンの材料になります。
- 朝の光を浴びる:体内時計がリセットされ、夜に眠気が訪れやすくなります。
小さな一歩でも、続ければ確実に「朝がラクになる体質」に近づけます。
どうしても朝がつらいと感じたら
 これまでご紹介した生活習慣の見直しやセルフケアを試しても、なかなか朝がラクにならない場合があります。その背景には、睡眠障害やうつ病など、専門的なケアが必要な心身の不調が隠れていることも少なくありません。ここでは、医療機関に相談すべきサインと、当院でできるサポートについてご紹介します。
これまでご紹介した生活習慣の見直しやセルフケアを試しても、なかなか朝がラクにならない場合があります。その背景には、睡眠障害やうつ病など、専門的なケアが必要な心身の不調が隠れていることも少なくありません。ここでは、医療機関に相談すべきサインと、当院でできるサポートについてご紹介します。
医療機関に相談を検討すべきサイン
- 2週間以上、朝の強い倦怠感や気分の落ち込みが続いている
- 生活リズムを整えても改善が見られない
- 日中も強い眠気や集中力の低下がある
- 仕事・学業・家庭生活に支障が出始めている
専門家と一緒に解決を目指す
 当院では、まず丁寧にお話をうかがい、必要に応じて診断や治療をご提案します。うつ病や睡眠障害と診断された場合、「休むこと」も大切な回復の一歩です。カウンセリングや薬物療法だけでなく、生活リズムの改善指導やストレスケアも行い、あなたの“朝”を取り戻すお手伝いをします。
当院では、まず丁寧にお話をうかがい、必要に応じて診断や治療をご提案します。うつ病や睡眠障害と診断された場合、「休むこと」も大切な回復の一歩です。カウンセリングや薬物療法だけでなく、生活リズムの改善指導やストレスケアも行い、あなたの“朝”を取り戻すお手伝いをします。
堺そらはねメンタルクリニックでは、心の不調が原因となる睡眠のお悩みに対応する睡眠外来を設けています。小さなことでも構いませんので、ぜひご相談ください。未然に病気を防ぐお手伝いができれば、私たちにとっても何よりの喜びです。






